「エンディングノートに『財産は長男に全部任せる』って書いたから大丈夫です。」
相続のご相談で、こんなふうにおっしゃる方が少なくありません。ですが、ここで大事なことをお伝えしなければなりません。
エンディングノートは、法的な効力がある“遺言書”ではありません!
この誤解のまま大切な相続を迎えてしまうと、想定外のトラブルが発生する可能性があります。今回は、エンディングノートと遺言書の違いや、それぞれの役割について詳しく解説します。
エンディングノートとは?
エンディングノートは、自分が亡くなった後に家族や関係者に伝えたいことを自由に記しておくノートです。最近では書店やインターネットで専用のエンディングノートが販売されており、「自分らしい最期」を考えるきっかけとして広く利用されています。
記載内容の例:
- これまでの人生の振り返り
- 医療や介護についての希望
- 葬儀の希望(形式・場所・費用など)
- 親しい人へのメッセージ
- 財産の概要(銀行口座、不動産、保険など)
これらは、遺された家族があなたの意思を汲み取るための大切な情報源となります。ただし、あくまで“参考情報”であり、法的な効力はありません。
遺言書とは?
一方、遺言書は法的な手続きに基づいて作成された「正式な遺志の表明」です。自分の財産を誰に、どのように分けるのかを明確に記載し、法律で定められた形式に従っていれば、遺産分割の際に強い効力を持ちます。
遺言書には主に以下のような種類があります:
- 自筆証書遺言
本人が全文・日付・署名を自筆で書く方法。2020年からは法務局での保管制度も利用可能に。 - 公正証書遺言
公証人が作成する方式。最も安全で確実とされています。遺言内容が秘密にされつつも、法律的な不備が起こりにくい。 - 秘密証書遺言
本人が作成した文書を封印し、公証人に提出する方法。あまり使われていません。
いずれの方式も、民法で定められた形式や要件を満たしていなければ、無効とされる場合があります。
エンディングノートと遺言書、それぞれの使い分け方
両方に役割があり、どちらも大切です。ただし、目的は異なります。
| 種類 | 法的効力 | 主な目的 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エンディングノート | なし | 想い・希望を伝える | 気軽に書けるが、相続には使えない |
| 遺言書 | あり | 財産の分配を法的に定める | 書き方に注意が必要、専門家の確認が安心 |
まとめ:「想い」も「お金」も、両方大切に
エンディングノートは、ご家族へのメッセージや希望を伝えるとても素敵なツールです。ですが、それだけでは相続のトラブルは防げません。
財産の分け方については、法的に有効な遺言書をきちんと準備することで、後々の相続人間の争いや手続きの煩雑さを減らすことができます。
「エンディングノートに書いたから安心」と思っていた方は、これを機にぜひ、専門家と一緒に遺言書の作成を検討してみてください。
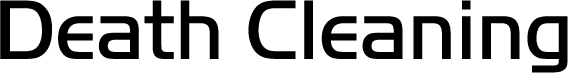
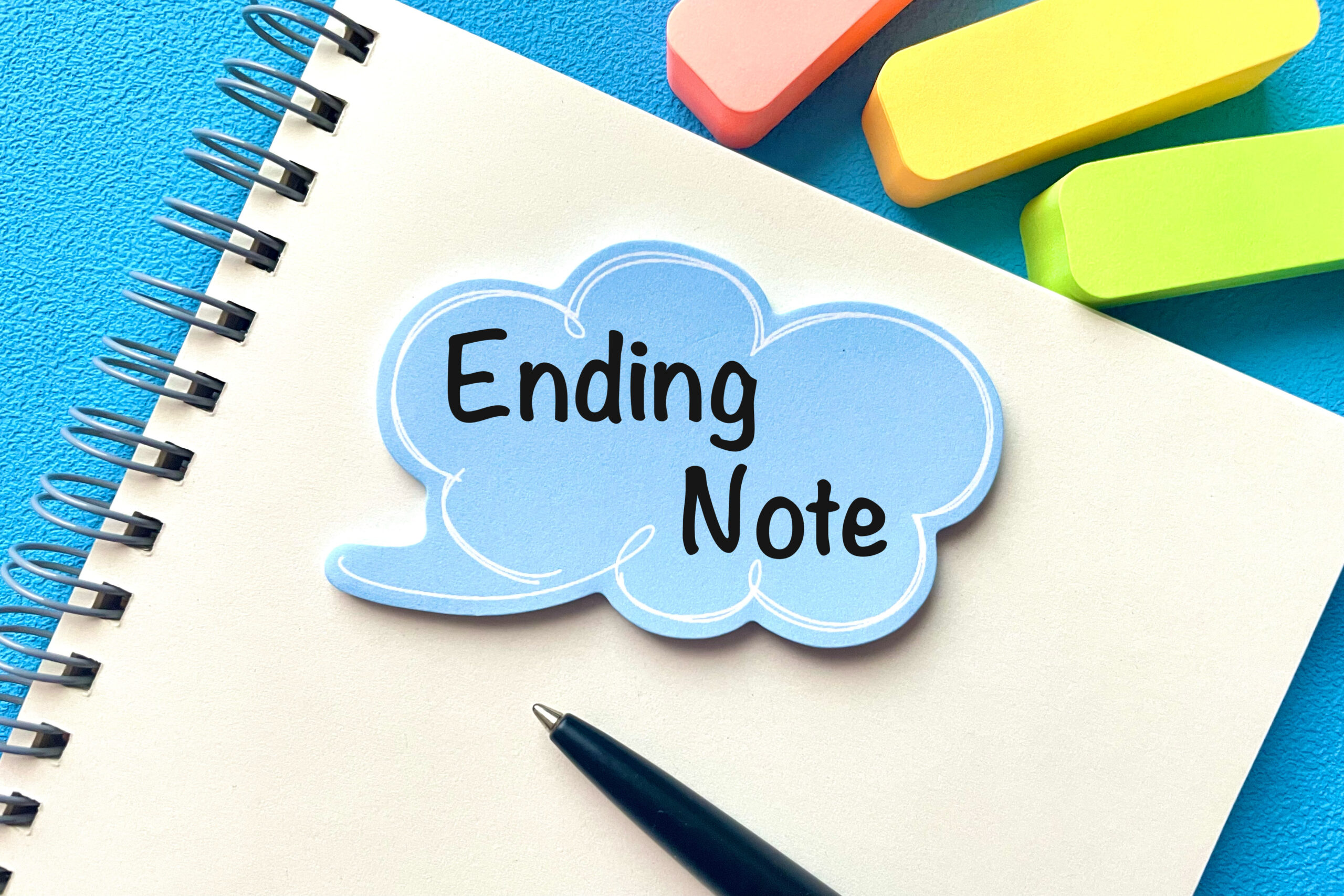


コメント