渋谷駅の銅像の下で、じっと飼い主の帰りを待ち続けた一匹の秋田犬。
それが、忠犬ハチ公です。
ハチ公は、亡き飼い主を信じ、約10年間、毎日渋谷駅に通い続けたといいます。
その姿は今も語り継がれ、日本人の心を打ち続けています。
でも、ふと思うのです。
もし、飼い主の上野博士が終活をしていたら?
ハチ公は、もっと安心して、温かい場所で生きることができたかもしれません。
今回は、ハチ公の生涯をたどりながら、ペットの未来を守る終活の方法について考えてみましょう。
🐾 ハチ公の生涯:ひとりぼっちになった理由
1923年、秋田県で生まれたハチは、東京帝国大学(現在の東大)の教授・上野英三郎博士の元へやってきました。
博士はハチをとてもかわいがり、毎朝一緒に散歩し、出勤する渋谷駅までハチが送り迎えするのが日課でした。
ところが、ある日突然・・
1925年、上野博士は大学で急逝します。
ハチはその事実を知らず、ただ「今日も帰ってくる」と信じて、
約10年間、毎日渋谷駅で博士を待ち続けました。
家族のように愛されたハチ。でも、その“家族”がいなくなったとき、ハチの生活は大きく変わってしまったのです。
🐶 ハチ公に必要だった「ペットのための終活」
もし上野博士が、万が一のときのためにハチの将来を託す準備をしていたら――
ハチの人生(犬生)は違ったかもしれません。
飼い主としてできる準備は、今の時代ならいくつもあります。
ペットの世話を託す「ペット信託」や「負担付遺贈」
「自分が亡くなったあと、ハチの世話を○○さんにお願いし、飼育費用として100万円を遺す」
こんな風に、お金と一緒に“お世話の責任”も託すことができる制度があります。
これを「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」といい、
さらに信頼できる第三者を通じて管理してもらう仕組みが「ペット信託」です。
ハチ公も、こうした形で新たな飼い主の元へ安心して引き取られていれば、
駅で何年も帰りを待つことはなかったでしょう。
飼育費用の準備も、忘れずに
犬の一生には、100万円以上の飼育費がかかると言われています。
特に高齢期には医療費もかかります。
ペットのために生命保険や信託を活用し、必要な費用を準備しておくことも、終活の一環です。
エンディングノートで「想い」を伝える
エンディングノートには、
・ハチの好きな食べ物
・散歩の時間や場所
・苦手なことや注意点
など、細かいけれど重要な情報を書くことができます。
もし上野博士がこれを残していれば、
新たにハチを世話する人も、博士の気持ちを引き継ぎながら接することができたでしょう。
ペットも“家族”として守る時代へ
ペットは法律上「物」として扱われますが、
私たちにとっては、かけがえのない「家族」です。
ハチ公の物語は、感動的であると同時に、
私たちに「飼い主としての責任とは何か?」を問いかけてくれる物語でもあります。
まとめ:ハチ公のような想いを、もう誰にもさせないために
上野博士の死を知らずに、毎日駅で待ち続けたハチ。
その姿は美談でありながら、一匹の犬が背負った“喪失”の物語でもあります。
だからこそ、私たちは学ぶべきなのです。
「自分に何かあったとき、この子はどうなるのか?」
その問いから始まるのが、ペットのための終活です。
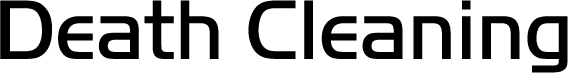

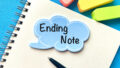
コメント