〜令和の相続、まだ昭和の手続きしてませんか?〜
「じゃあ、順番にハンコ押していきましょうか」
——遺産分割協議書を囲んで、親族間で始まる“ハンコリレー”。
これ、昔ながらの風景としてはほっこり見えるかもしれません。
でも、令和の今、それって本当に必要ですか?
今回は、意外と多くの人が勘違いしている「相続手続きのハンコ文化」について、ちょっと笑いも交えながら解説していきます。
そもそも“ハンコリレー”って何?
相続手続きでは、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印が必要です。
そのため、一人が書類に押印したら、それを次の相続人へ。
その人が押したら、さらに次へ——と、まるでリレーのように書類が旅をします。
これが通称「ハンコリレー」。
でもこの“リレー”、意外とトラブルの元なんです。
よくある“ハンコリレー事故”3選
書類がどこかに消える
「確かに郵送したはずなんだけど…」
郵便事故で書類紛失。ゼロからやり直し…。
順番待ちで何週間もかかる
「忙しいから来週でいい?」と先延ばしにされ、1人の押印待ちで1ヶ月ストップ。
勝手に内容が修正されてた
先に押した人の確認なしに、誰かが一部内容を修正してしまい、無効に。
こんなことが実際にあるんです。
昭和のスタイル、令和では非効率?
一昔前までは、親戚同士も近くに住んでいたり、集まりやすかったので、この方法でも何とかなっていました。
でも今は:
- 相続人が全国に散らばっている
- LINEやメールでは連絡がつくのに、紙のやり取りは面倒
- 実印なんて普段使わないから、どこにあるか分からない!
…と、“昔ながら”のやり方が今の時代に合わなくなってきています。
じゃあ、どうすればいいの?
◆ 方法①:公正証書遺言でそもそも“協議”を不要にする
被相続人が生前に公正証書遺言を作成しておけば、
遺産分割協議そのものが不要になり、ハンコリレーもナシ!
相続人が多い場合や、遠方に住んでいる家族がいる場合に特におすすめです。
◆ 方法②:司法書士・行政書士に“一括サポート”を依頼する
プロに依頼すれば、書類の準備から押印の管理まで一括で行ってくれます。
郵送でのやり取りも、ミスが起きないようきちんと追跡・管理してくれます。
手間を省きたい、確実に終わらせたい人向け。
◆ 方法③:オンライン手続きやデジタル署名の活用(今後の展望)
現在、マイナンバーカードやデジタルIDを活用した相続手続きのオンライン化が進められています。
まだ一般化はしていないものの、将来的には「紙もハンコもナシ」の時代が来るかも。
「ハンコ文化」は悪者じゃない。でも…
もちろん、紙とハンコのやり取りには“安心感”や“正式感”があります。
「やっぱり実印が押されてると、気持ちが引き締まる」
「親戚同士で順番に確認するのも、一種の儀式みたいでいい」
そんな声もあります。
ただ、大事なのは“方法”ではなく“中身”と“効率”。
時間も労力も有限です。
無駄なトラブルやストレスを防ぐためには、“やり方”を見直すことも必要なんです。
最後に一言
もし今、「そろそろ親の相続の準備、考えなきゃな…」と思っているなら、
その書類、ハンコ、送付先リストを用意する前に、一度立ち止まってみてください。
もしかしたら、もっとラクで、もっとスムーズな方法があるかもしれませんよ。
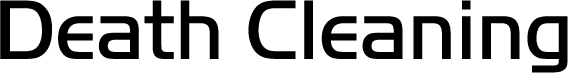
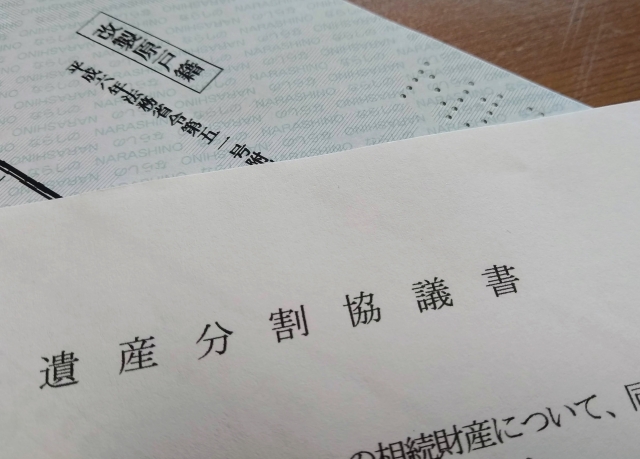


コメント