相続放棄をすれば、相続人でなくなり、借金も資産も関係なくなる――そう思っている方がほとんどだと思います。
しかし実際には、相続放棄をした後も、一定期間は被相続人の財産を管理する義務が残るのです。
「え?放棄したのに責任があるの?」
「管理って具体的に何をすればいいの?」
このような疑問を持たれる方のために、今回は、放棄後に残る「相続財産の管理義務」について、法律の根拠から実務対応まで徹底的に解説します。
相続放棄の基本をおさらい
相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、「自分は相続人ではない」とする制度です。相続放棄が認められると、法律上最初から相続人でなかったことになるとされます(民法第939条)。
つまり、相続放棄をすれば:
- 財産(不動産、預貯金、有価証券など)は受け取れない
- 負債(借金、保証債務など)も引き継がない
- 手続が完了すれば、それ以上の関与は基本的に不要
――となるのが通常の理解です。
しかし、ここに例外があるのです。
ただし、相続放棄制度の趣旨は、相続による不利益を回避する。ということは重視されています。
民法940条に定められた「管理義務」とは?
■ 法律の条文
民法第940条
- 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
- 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
占有とは、「ある物を実際に使ったり、持っていたりすること」(自己に所有権がある、ないは関係ない。)です。
もっと簡単に言うと・・・「この物は今、自分が持ってるよ!」っていう状態のことです。
例えば、
『iPhone16e買っちゃった。』
iPhone16eの所有権は、自分。占有しているのも自分。
『ファミコンのカセットを友達Aから借りて友達Bに貸していて、友達Bがゲームしている。』(例えが古いか?)
ファミコンのカセットの所有権は、友達A。占有しているのは、自分(貸主:間接占有)と友達B(借主:直接占有)
『友達の時計を盗んで使ってる・・』(ダメですよ)
時計の所有権は、友達。占有しているのは、自分。
つまり、相続放棄をしても、相続財産に属する財産を現に占有(今、自分が持ってるよ)しているとき、相続人や相続財産清算人が現れて財産の管理を始めるまでは、放棄した人が管理をしなければならないということです。
被相続人が、生前に住んでいた家が、死亡により空き家となった場合、相続放棄しても、次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。と、なっていたが、現在は、占有してなければ、管理義務はありません。
占有している相続財産がなければ、以下は関係ありません。
管理義務の内容と義務の程度
相続放棄の時点で相続財産に属する財産を現に占有している者には、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。) のために、財産の滅失又は損傷をしないという意味での保存義務が課されていて、財産の現状を維持するために必要な行為は含みません。
また、義務の程度は、「自己の財産におけるのと同一の注意」となっています。
自己の財産におけるのと同一の注意とは、人の物を扱うときでも、自分の物と同じくらい大事に、丁寧に扱ってくださいね。という程度です。
参考:「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」・・「他人の物だから完璧に管理しないと!」という注意義務です。これより、自己の財産におけるのと同一の注意は、軽い注意義務です。
管理義務が終わるのはいつ?
原則、放棄した人が相続人又は相続財産法人(相続人がいない場合)に当該財産を引き渡して占有を移転したときに終了します。
まとめ
相続放棄をした後にも、一時的な相続財産の管理義務がある場合があるというのは、あまり知られていない大切なポイントです。
この管理義務は「相続を放棄したのに責任だけ負わされる」と感じる方もいるかもしれませんが、これはあくまで社会的・法的な空白期間を補うための「一時的な義務」にすぎません。
しかし、対応を誤るとトラブルの元になることもありますので、少しでも不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。
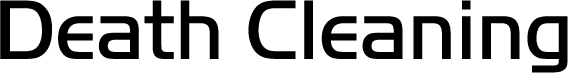

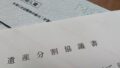

コメント