遺留分をめぐる相続の落とし穴
相続の話になると、「遺言書があるから安心!」と思う人が多いかもしれません。しかし、たとえ遺言書があっても、一定の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という権利が認められています。
今回は、遺留分についてわかりやすく解説し、トラブルを避けるためのポイントを紹介します。
遺留分とは?
遺留分とは、法律で保証された「最低限の相続分」のことです。もし、被相続人(亡くなった方)が遺言で「全財産を特定の人に相続させる」としていても、他の相続人は遺留分を請求できます。
つまり、被相続人の自由な財産の処分を制限し、残された相続人が最低限の遺産を受け取れるようにする制度です。
遺留分の対象となる相続人
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 配偶者(夫や妻)
- 子(またはその代襲相続人)(子が先に亡くなっている場合は孫)
- 直系尊属(父母・祖父母) ※ただし、子がいる場合は対象外
兄弟姉妹には遺留分がありません!
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書に何も書かれていなければ相続財産をもらう権利はありません。
遺留分の割合
遺留分は、法定相続分(法律で決められた相続割合)の一定割合です。
- 直系尊属のみが相続人 → 法定相続分の1/3
- 上記以外(配偶者・子などがいる場合) → 法定相続分の1/2
例えば、父親が亡くなり、相続人が妻と子1人の場合、法定相続分は妻1/2、子1/2です。
しかし、仮に遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書かれていた場合、子には遺留分として法定相続分1/2のさらに1/2(=1/4)が保証されています。
つまり、遺産総額が4000万円なら、子は、1,000万円(4000万円×1/4)を請求できるのです。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分は自動的に受け取れるわけではありません。遺留分が侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きをしないといけません。
請求の期限に注意!
- 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内
- 相続開始から10年以内
この期限を過ぎると、遺留分を請求できなくなります。
遺留分トラブルを避けるための対策
遺留分が原因で相続トラブルになるケースは少なくありません。事前に次の対策をしておくと安心です。
遺言書を作成する(遺留分に配慮)
遺言書に「どのように相続させるか」を明記しつつ、遺留分も考慮することで、相続人同士の争いを防げます。
事前に話し合う
生前に相続人と話し合い、納得してもらうことで、後の争いを避けられる可能性があります。
生命保険や贈与を活用する
遺留分の対象となる財産は「遺産」ですが、生命保険金や生前贈与を活用することで、特定の相続人に多くの財産を残す方法もあります。
詳しくは、弁護士又は税理士にご相談ください。
まとめ
遺留分は、相続人が最低限の遺産を受け取るための権利です。ただし、請求しないと権利が消滅してしまうため、注意が必要です。
一方で、遺留分を考慮しない遺言書が原因でトラブルになることも多いため、相続対策として、遺言書の作成や生前の話し合いを検討するとよいでしょう。
相続は人生の大切な問題。しっかりと知識を身につけ、円満な相続を実現しましょう!
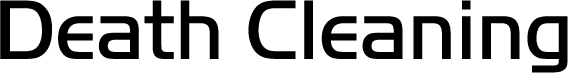
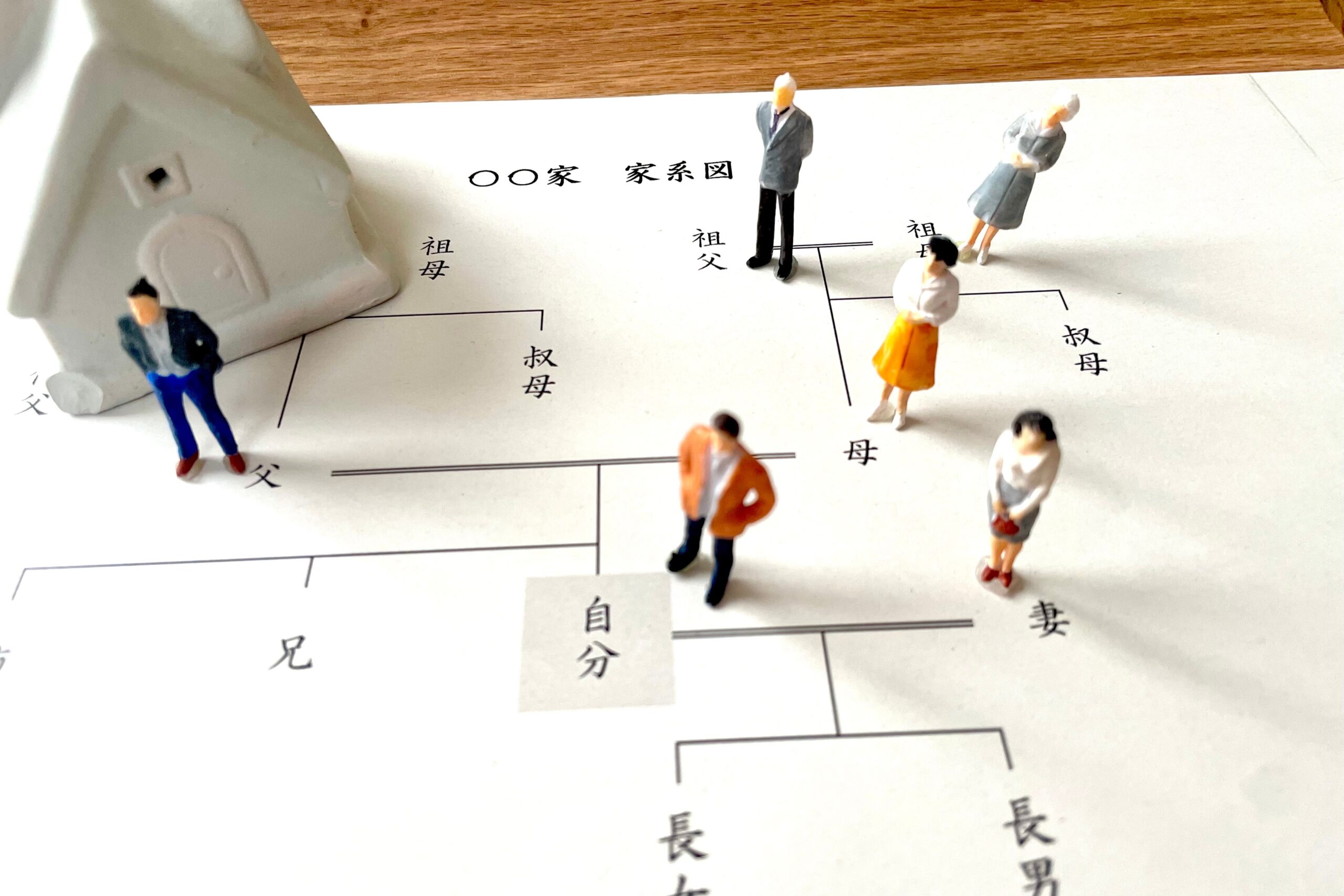


コメント