明治民法(1898年施行)では、家制度(家督相続)が採用されており、家長(戸主)の地位や財産を継承する者を「家督相続人」と呼びました。
私のばーちゃんが、家督相続人と以前の記事で書きました・・・
ばーちゃんは、第二子(長男がいる、ばーちゃんは、長女)ですが、どー考えても名前が第一子につけるような名前です。
そして、長男を差し置いて、家督を相続したようです・・・・
家督相続とは?
家督相続とは、家の財産・地位・権利義務を一括して特定の相続人が承継する制度です。
現代の遺産相続(法定相続)とは異なり、家の存続を重視(現在は、個人主義です。憲法で保障)していたため、原則として戸主の死亡または隠居時に、家督相続人が単独で相続する仕組みでした。
家督相続人の決定ルール
家督相続人は、基本的に長男が優先されました。
具体的には、以下の順位で家督相続人が決定されました。
- 戸主の直系卑属(長男が最優先)
- 戸主の長男が原則として家督相続人
- 長男がいない場合は次男・三男の順で継承
- 長男が死亡している場合、その長男の子(直系卑属)が相続
- 直系尊属(戸主の親など)
- 戸主に男子の直系卑属がいない場合、直系尊属(父)が家督相続
- 兄弟姉妹
- 直系卑属・直系尊属がいない場合、戸主の弟(兄弟のうち最年長者)が家督相続
- 内妻(未亡人)の相続は原則なし
- 妻は戸主の家に入る立場のため、原則として家督相続人にならない
- ただし、夫の死亡時に未成年の子がいる場合、妻が「家督相続人の法定後見人」となることもあった
このように、基本的に「家の跡継ぎ」が家督を継ぐという考え方が強かったのが特徴です。
家督相続の特徴と現代との違い
| 項目 | 明治民法(家督相続) | 現代民法(現行相続制度) |
|---|
| 相続方法 | 単独相続 | 共同相続(法定相続分あり) |
| 相続人の決定 | 長男(戸主の直系卑属が優先) | 配偶者+子供(均等分割) |
| 相続の開始 | 戸主の死亡 or 隠居時 | 被相続人の死亡時 |
| 相続財産 | すべての財産+戸主の地位 | 財産のみ(家制度なし) |
| 女性の相続権 | 原則なし(一部例外) | 男女平等 |
現代の相続制度では、家督制度は廃止され、財産は法定相続人で分割相続される形になっています。
家督相続の廃止(戦後の民法改正)
1947年(昭和22年)の民法改正により、家制度は廃止され、現在の「均分相続」の仕組みに変更されました。
これにより、長男がすべてを相続する家督相続制度は消滅し、配偶者・子供が平等に相続する現行制度が確立しました。
まとめ
- 明治民法では、家督相続人が戸主の地位や財産を単独で承継した
- 原則として長男が家督相続人となり、次男・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続
- 女性の家督相続権は制限されていた(例外あり)
- 戦後の民法改正(1947年)で家制度が廃止され、現行の相続制度に移行
現在では、法定相続分に基づく共同相続が基本になっています。
ばーちゃんが、家督相続した謎は、私の推測ですが・・・長男を廃嫡して、次男以降が幼いなどの理由でばーちゃんが家督を相続することが受理されたのではないかと・・・思われます。
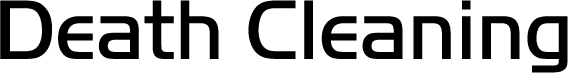



コメント