相続の際、遺産を公平に分配するために考慮される要素として「特別受益」「寄与分」「特別の寄与」があります。これらは相続人や特定の親族が被相続人(亡くなった方)に対して行った経済的・貢献的な行為を考慮し、公平な遺産分配を行うための制度です。本記事では、それぞれの概要と具体的な事例について詳しく解説します。
特別受益とは?
特別受益とは、相続人のうち、被相続人から生前に特別な財産の贈与や経済的援助を受けた場合に、その受けた財産を相続財産に加算して考慮する制度です。これにより、相続人間の公平性が保たれます。
特別受益の具体例
- 生前贈与:被相続人から相続人に対して住宅購入資金や学費の援助を受けた場合
- 結婚・養子縁組の際の持参金:特定の相続人が結婚時に多額の金銭や財産を受け取った場合
- 事業資金の援助:被相続人が特定の相続人に事業資金を援助し、その結果として他の相続人と大きな財産格差が生じる場合
具体的相続分の計算方法
特別受益に該当する財産は「みなし相続財産」とされ、相続財産に加算して分配を行います。計算方法は以下のようになります。
(相続開始時の遺産総額+特別受益の額)✖️法定相続分(or指定相続分)=各相続人の相続分
特別受益を受けた相続人
上記相続分ー特別受益の額=具体的相続分
特別受益を受けなかった相続人
上記相続分=具体的相続分
特別受益を受けた相続人は、受け取った財産分を差し引いた額を相続できることになります。
寄与分とは?
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした人が、その貢献度に応じて遺産を多く受け取ることができる制度です。
寄与分が認められる条件
- 被相続人の財産が、寄与したことによって明確に増加または維持されたこと
- 通常の親族関係に基づく扶養義務の範囲を超えた貢献であること
寄与分の具体例
- 事業の支援:被相続人が営む事業に無償で長期間従事し、事業の発展に寄与した
- 介護・看護:特定の相続人が長年にわたって病気の被相続人を看護し、介護費用を抑えることに貢献した
- 財産管理:被相続人の財産を管理し、適切な運用を行って資産価値を維持・向上させた
具体的相続分の計算方法
寄与分が認められた場合、遺産分割時にその貢献度を金銭的に評価し、他の相続人とのバランスを考慮して遺産分配が行われます。
(相続開始時の遺産総額ー寄与分の額)✖️法定相続分(or指定相続分)=各相続人の相続分
寄与した相続人
上記相続分+寄与分の額=具体的相続分
寄与していない相続人
上記相続分=具体的相続分
寄与分の評価には、共同相続人の協議で決められます。議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が寄与分を定める。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
つまり、遺産すべて遺贈された場合は、寄与分は考慮できません。
特別の寄与とは?
特別の寄与とは、2019年の民法改正によって導入された制度で、相続人ではない親族が被相続人の介護や財産管理に貢献した場合に、相続人に対して金銭請求できる制度です。
特別の寄与が認められる条件
- 被相続人の財産維持や管理、生活支援に貢献したこと
- 相続人以外の親族(例:長男の妻、義理の娘、孫など)が貢献したこと
- 通常の扶養義務の範囲を超える寄与であること
特別の寄与の具体例
- 長男の妻が義父の介護を10年間続けた
- 娘婿が被相続人の財産管理を長年手助けした
- 孫が同居しながら長期間、療養看護を行った
特別寄与料の請求方法
相続開始後、特別寄与者は相続人に対して「特別寄与料」の請求を行うことができます。この請求は、相続が開始してから 6か月以内 に行う必要があります。
特別寄与料は、当事者間の協議で決めます。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
つまり、これも、遺産すべて遺贈された場合は、特別の寄与分は考慮できません。
まとめ
相続では、単純に遺産を分けるだけでなく、被相続人の生前の財産移転や相続人・親族の貢献を考慮する制度が存在します。
- 特別受益:生前贈与を受けた相続人の公平性を保つための制度
- 寄与分:相続人の中で特別に貢献した人に多めに分配される制度
- 特別の寄与:相続人ではない親族が貢献した場合に金銭請求できる制度
これらの制度を正しく理解し、相続争いを避けるためにも、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
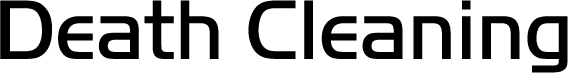



コメント